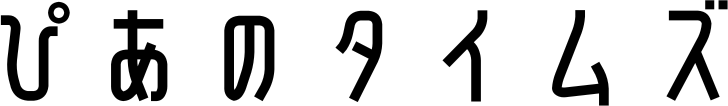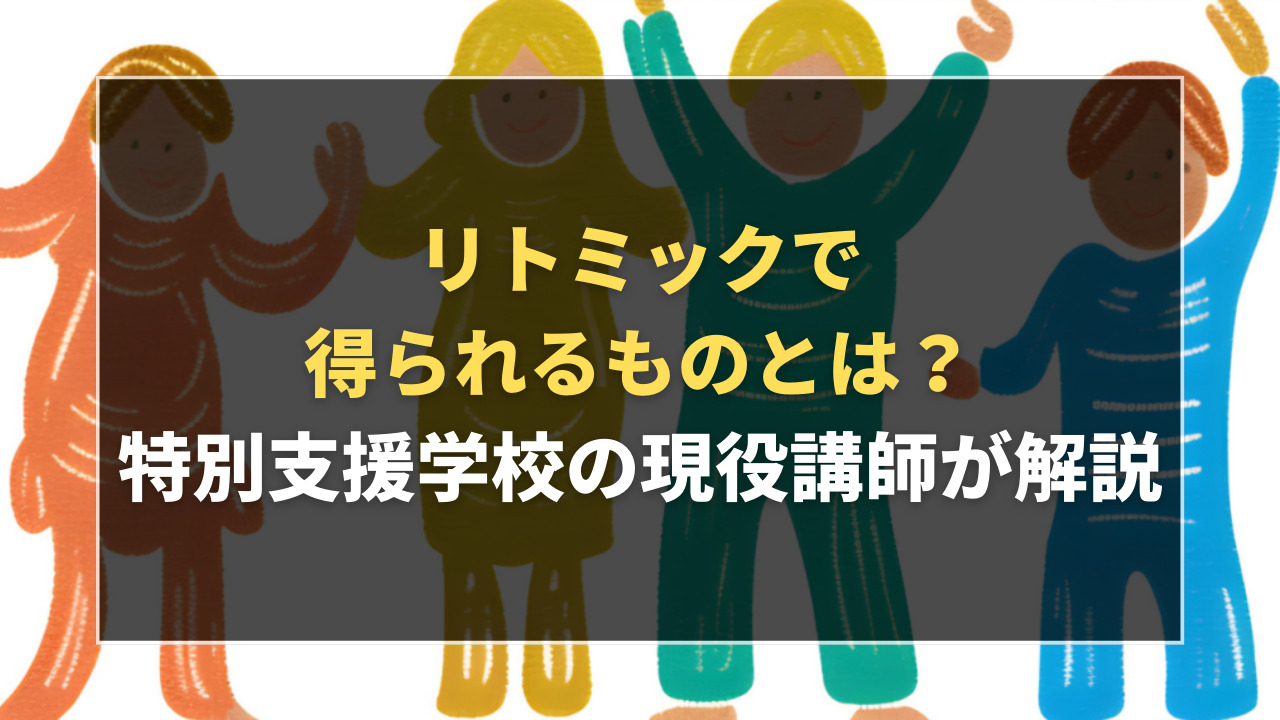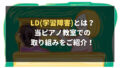リトミックで得られるものとは?
リトミックとは、音楽教育家であるダルクローズが考案した音楽教育法の一つです。
音楽に合わせて身体を動かしたり、歌ったり、楽器演奏の基礎を身につけたりすることで、子どもたちのリズム感や音楽的感覚を育てることを目的としています。リトミックは人間の発達に合わせたプログラムが組まれており、子供たちが自然に楽しめるようになっています。そのため、子供たちは音楽的な表現力だけでなく、好奇心や創造性も高めることが期待されます。
特別支援学校でのリトミック授業の実施
私の勤務する特別支援学校では、小学生から高校生までリトミックを取り入れた授業を実施しています。特に特別支援学校では、感覚統合を目的の一つとしています。感覚統合とは、五感から得た情報を正しく統合し、身体の使い方や社会性などの重要な能力をを育むことができる働きのことです。感覚統合がうまく機能することで、子供たちは運動能力や協調性を養うことが期待できます。
授業では、曲に合わせて子どもたちが歩く、走る、回転する、避難する、揺れる、立つ、座る、ジャンプするなど、多彩な身体の動きを取り入れます。また、手と足との複合リズムや速度変化、音の「高い・低い」なども意識しています。子どもたちは、聴覚的な情報をもとに身体を動かすことで感覚統合を促進し、コミュニケーション能力も磨いてきます。
リトミックを通じて実感した生徒の成長

日常の動作がスムーズに
授業では、ある合図でリーダーと同じ動作をするなど、コミュニケーション能力を高める取り組みも行われます。このような取り組みを継続すると、生徒たちの立つ、座るなどの基本的な動作がスムーズになったことが実感できました。これは、授業がゲーム感覚で進められるため、子どもたちが楽しみながら身体を動かすことができるからです。
生徒の「苦手」へのアプローチ
生徒の中には、例えば自閉症スペクトラム症の生徒など、急な変化やコミュニケーションが苦手な子供たちがいます。あらかじめ変化を伝え、予測可能なリトミックは安心感を与えることができます。リトミックの取り組みが、さまざまな生徒の苦手なことへのストレスを軽減することに繋がっています。
リトミックを通じて、身体の反応や感覚統合能力を養い、自分を表現する力や集中力も向上するとされています。また、リトミックは音楽や運動を通じたコミュニケーションの一つなので、チームワークや協調性を身につけることができます。
脳の発達への影響
リトミックには脳の発達にも良い影響があるとされています。例えば、リズムに合わせて動くことで、脳内の神経細胞が活発になり、神経伝達物質の分泌が促されます。また、右脳と左脳の協調を促し、創造力や問題解決能力も高めるとされています。
授業で工夫していること

リトミックの授業においては、順番や曲の選び方など、こだわりを持っている部分が数多くあります。
例えば、幼児向けの曲を使用するのではなく、年齢に応じたクオリティの高い曲を使用することで子どもたちの興味を引き出し、授業への集中力をキープしています。例えば、威風堂々、天国と地獄、ショパンのノクターン、子犬のワルツ、乗馬アラベスクなどを使用しています。
最後に
今後も生徒たちの成長に合わせたプログラムを作り、モチベーションを高め、学習意欲を向上させていきたいと考えています。生徒たちが日常生活の中で音楽や身体の動きを楽しみ、自信をもって挑戦できるよう、音楽的感性を育てることを目指して今後も精進していきます。